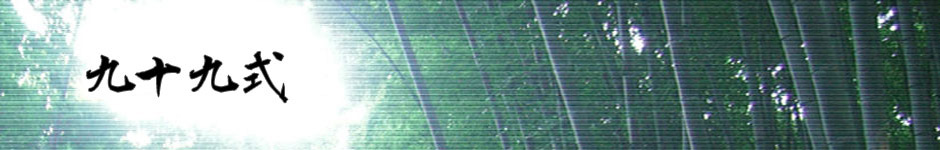いもうと日記完結編
皆さん、本日9月6日が何の日だかしっていますか。え、知らない?
「妹の日」ですよ。妹の日。
あ、閉じないでください。本当です。グーグルで調べてください。
妹の日
現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した「兄弟型姉妹型」研究の第一人者で漫画家の畑田国男さんの提唱により1991(平成3)年に制定。 妹の可憐さを象徴する乙女座(8月27日~9月23日)の中間の日の前日。 毎年3名ずつの女性に「妹の日大賞」を授与しています。 12月6日が「姉の日」となっています。
ほほぉー。ツッコミどころというか、数々のびっくりポイントに彩られた説明ですが、まぁとにかく、妹って素晴らしい! ほらいつもと同じ道だってなんか見つけよう! という日なのです。今日は、そんな妹の日にちなんで、例の大好評企画が帰ってまいりました。
「いもうと日記完結編・夏の拡大スペシャル」です。(なるべく完全版のほうをお読みください)
去り行く夏を惜しむように、街中のセミが一斉にないている。2002年8月31日。今日は、I市とE区で大きな花火大会がある日だ。夏休みも終わりにさしかかり、夏を彩る最後のイベントを、街中が楽しみにしていた。
当然我が家もその例外ではなく、前日から気合の入りまくった妹は「明日の花火を見るには、どこの場所がいいか」としつこく訊いてきた。仕方なく道路地図を引っ張り出してきて、打ち上げ場所からの距離と地形、風向き等を説明してやった。あまり伝わってないようで、「花火って、下からみるとひらべったいの?」と真顔で訊いてきたので、僕は思わず笑ってしまった。
 翌日。僕がうちわをパタパタとやりながら、居間でプレステをやっていると、妹は真っ赤な浴衣を来て現れた。
翌日。僕がうちわをパタパタとやりながら、居間でプレステをやっていると、妹は真っ赤な浴衣を来て現れた。
「なんか部屋でごそごそしてると思ったら…。なんだそれ。」
「へっへっへー。いいでしょー。テレビで使ったのもらってきちゃった。」
「それはいいとしてお前、帯が後ろ前だよ。」
僕は、なぜか前にきていた帯の結び目をぐるりと回して、背中にうちわをさしてやった。
「んー。ところで、おにいちゃんは行かないの?はなび。」
「ああ、行くよ。」
「誰と行くの?かのじょー?かのじょー?」
「いや別にそういう関係じゃないけど。」
「…。女のコなんだ?」
「え? ああ、うん。」
「フーン、フーン。良かったじゃん!いいもん、そんじゃ連れてってあげない!」
別に連れてってくれと頼んだ覚えはないんだけど。と言う暇もなく、妹はスニーカーを突っかけてさっさと出て行ってしまった。
「おいっ。」
僕は妹の後姿に向かって呼びかけたが、返事の代わりに、玄関の扉が閉まる音が聞こえた。
「浴衣にスニーカーなのかよ…。」
打ち上げスタートを30分後に控えて、S駅周辺はかなりの人込みでごった返していた。
「こうして2人で話すのって随分久しぶりだね」
僕のとなりには、大学への行き帰りをいつも一緒に歩いた女のコがいた。僕らはあの頃のように人込みの中を並んで歩きながら、とりとめもなく色々な話をした。近況報告、大学の頃の話、家族の話、日常系トホホ失敗談、自虐ネタ、非モテネタ、時事ネタ、etc…。
彼女は現在、TV番組の配給会社につとめていて、海外ドラマの放映権の買い付けの仕事をしているそうだ。
「やっぱ語学力が生かせる仕事につけて良かったよ。」
「俺も結構生かしてるよ。」
「どんな時?」
「酔っ払いのアメリカ人が食い逃げした時とか。」
「あはは、何それー!」
屈託の無い彼女の笑顔は、ちっとも変わっていなかった。そんな他愛の無い話をしながらも、僕らの距離は少しづつ縮まっていった。肩と肩とが触れ合うくらいの距離になった時、ふと手を握ってみたくなった。驚くかな。手を引っ込められちゃうだろうか。
意識し始めると、急にてのひらが汗ばんできた気がして、僕は何度もジーンズで手をこすった。
道路いっぱいに広がって歩いている中学生とすれ違う時に、僕は彼女の手を引いた。すれ違ってからも、僕は手を離さなかった。彼女も僕の手を握りかえした。
その時、僕のケイタイが鳴り響いた。
曲がミニモニである事を思い出した僕は、彼女の手を離して素早く電話に出た。
「もしもしっ!?」
「あ、おにいちゃーん。今どこにいるの?」
「なんだお前か。俺も花火大会だよ。」
「むかえにきて…。」
「ハァ?(゚д゚) むかえにって…何行ってんだお前、一人で来たのか?」
「ともだちと、はぐれちゃったの。」
「じゃあ、その子に電話すればいいだろう。」
「バッグ落としたから、ケイタイもサイフもどっか行っちゃったんだよー。」
一体、何をやっているんだこいつは。
「おい、あのな…」
「だから今こうしゅう電話なんだけど、お兄ちゃんの番号と家の番号しか思い出せなくてそれで、ののおさいふ落としたから今100円しかもって無くて、100円しか入れてないからもう電話切れちゃうからむかえにプツッ…」
ツー、ツー、ツー。
公衆電話って…。一体どこの公衆電話だ?
「どうしたの?誰から?」彼女がいぶかしげに僕の顔をのぞきこんだ。
「いや、なんでもないよ。」
 いよいよ花火が始まった。オープニングから4号玉、5号玉が景気良く上がり、大音響と共に夏の夜空に大輪の花を咲かせている。
いよいよ花火が始まった。オープニングから4号玉、5号玉が景気良く上がり、大音響と共に夏の夜空に大輪の花を咲かせている。
僕らは人込みをかきわけ、やっとの思いで河川敷まで辿りついたが、当然座る場所は埋まっていた。二人は寄り添うように立って、夜空を見上げた。
「きれいだねー。」
「…ああ。」
彼女の声は耳に入っていたが、僕はさっきの電話が気になって仕方なかった。駅からこの河川敷に来るまで、商店街を抜けて15分くらいは歩いたよな…。知らない場所で一人か。誰かに気付かれたらパニックになるかも…。サイフごと落としたっていうし…。
「それでね、……ねえ、聞いてる?」
「え?ああ、ごめん何?」
「ううん、何でもないの。」
ドーン!パララララ…。この花火の大音声も、一人ぼっちの妹にとっては、ただただ不安を増幅させる雑音にしか聞こえないかもしれない。
「ごめん、ちょっと俺、急用が出来た。」
「えっ?ちょ、何ー!?」
「ごめん、また電話する!」
自分でも馬鹿な事をしているな、と思った。でも今更引き返せるわけもなかった。「ごめん!さっきの無し!」と言ってみても、僕らが手をつなぐことはもうないだろう。それに彼女は大人だから、一人でも帰れる。僕らはもう別々の道を歩んでいるのだ。
愛が地球を救えるというのは誇大妄想だ。たった一人の人間を救えるかどうかさえ、わからない。
でも、少なくとも今、僕の助けを必要としている存在がある。そして僕には今、妹を探すことができる。
僕は走り出した。
僕は赤や青に光る夜空を背に、必死で公衆電話を探した。前髪は額に貼りつき、Tシャツは体にまとわりついた。どだい、これだけ人がいるなかから、あんな小さいのを見つけるなんて無理なんじゃないのか。僕は、この花火大会には毎年100万人以上が集まるという事実を思い出して、軽いめまいに襲われた。
こうして見てみると、浴衣で花火大会に来る子も結構いることに気付いた。赤い浴衣を見るたびにドキっとして足を止めた。
ケイタイを見ると、既に探し始めて1時間近く経っていた。
ふと顔を上げると、小さな赤い後ろ姿が目に入った。背中には、僕の差したうちわがあった。間違いない。見つけた。
ちょうどそのとき、二人組の若い男が希美に声をかけようとしていた。
「おいっ。」
とっさに僕が声をあげると、妹と、二人組と、周囲の人達の目が僕を見た。僕は、ケンカになったらどうしよう、と身構えたが、妹が「おにいちゃん!」と僕に抱きつくと、彼らは舌打ちをしてどこかへ行ってしまった。
「おにいちゃん……おにいちゃん……うえぇ……」
緊張の糸が突然切れたからか、妹は堰を切ったように泣き出した。
「こら、鼻水付けるな。離れろ暑苦しい。」
周りの人の視線を感じたので、僕は妹を引きずって人込みを離れた。彼女は泣きやんでからも僕の腕をしっかりとつかんで離さなかった。
「ありがとね。ごめんね。」
全く、世話の焼ける。いつもこうして僕が助けている。今日だって僕がいなかったらどうなっていたことか。
気が付くと、花火は終わっていた。
「あんしんしたらおなかすいちゃったよ。」やれやれ。空腹を訴える妹をつれてコンビニへ入ると、花火帰りの人でごった返していた。店内の有線は、いつかの夏の歌を流していた。
君と夏の終わり 将来の夢 大きな希望 忘れない
10年後の8月 また出会えるのを 信じて
最高の思い出を…
あぁ 花火が夜空 きれいに咲いて ちょっとセツナク
あぁ 風が時間とともに 流れる
またはぐれないように手を引きながら菓子パンを物色していると、妹はレジ横の花火コーナーで足を止めた。
「ねえ、はなび。」
「ああ、誰かさんのせいでろくに見られなかったもんな。」と僕は皮肉を言ったのだが、希美は
「やろうぜー!」
と目を輝かせた。
僕らは、人の引いた川辺で、ささやかな花火大会を始めた。
両手に持ったり、ぐるぐる回したり、地面に白い字を書いたり。小さな打ち上げ花火もいくつかあった。 ひとしきり遊ぶと、最後には線香花火だけが残った。
「じゃあ、これやったら帰るぞ。」
「うん。」
僕は線香花火の束をよりわけて、希美に手渡した。
「ねぇお兄ちゃん…。」
「ん、なんだ。」
「また来年も、こうやって、こんな風に夏が来るのかなあ。」
「ああ、この花火大会は毎年恒例だからな。」
僕はカチン、とジッポーライターをはじいて返事をしたが、彼女がそんなことを訊いてるのじゃないってことは、知っていた。
この夏は、もう二度と帰らない。来年の夏は、今年の夏とは違う。
二人で一つ手に持った、せんこう花火。
「みんな、離れ離れになっちゃうよ…。」
妹の顔がくもった。僕は何と言って慰めてやればいいのか解らず、己の無力を感じた。
「残された人が笑顔で送らないと、卒業するほうも困っちゃうぞ。」
小学校の時、バレー部を卒業する時にもこういう事があった。人は出会いと別れを繰り返して大人になるというけれど。でも。
妹はだまってくちびるを噛んだ。
妹にも解る時が、いつかきっと来るだろう。
夏休みには、いつか終わりが来るものなんだ。
「10人の時がいちばん楽しかったかな…。」と妹が呟いた。
そうだな、あの頃は楽しかった。僕の呟きは風にのって流れて、消えた。
線香花火はジ・ジ……、と最後の火花を散らして、やがてぽとりと落ちた。
僕らの、長かった夏休みは終わろうとしていた。少し涼しくなった夜風は秋の匂いを運んで来て、妹の前髪を揺らした。その横顔がちょっと大人っぽくなったのに気付いた。そう言えば、希美ももう15歳、来年は高校生なのだ。希美が15歳だなんて、なんだか奇妙な気がした。希美はずっと13歳と14歳との間を行ったり来たりしているのが自然なように思えた。
「でももうすぐ秋が来るぞ。おイモの美味しい季節だぞ。」
「おいも! そっかー、しょくよくの秋だぜぇっ!」希美は元気にガッツポーズをとった。
「でもその前に、もっとかきごおり食べたい!」
その真夏の太陽のようなまぶしい笑顔を見て、僕はやっと気付いた。いつだって、この笑顔に癒されて、励まされて。 助けてもらっていたのは、ずっと僕の方だったんだ。
二人で一つ手に持った せんこう花火
あなたの瞳に映ってる火が
とても奇麗だわ
二人の心の中の せんこう花火
ずっと消えない花火にしようって
誓ってくれた
FOREVER
広告
よ、4,096文字っ!?