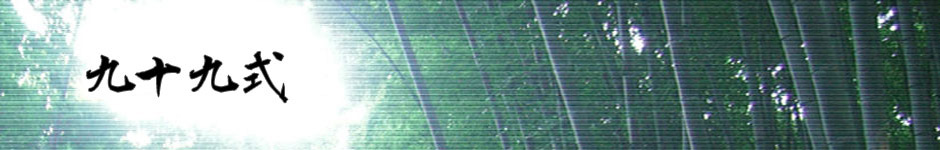「一度書いたブログ記事は修正しないのがマナー」という誤解
昨日書いた、「ドラッカーの詩というネットのデマ」について。
これがドラッカー作というのがデマであることと、その本当の作者について、サイコドクターさんのところで完璧に調査、実証されているので、僕の方では一読者、一ドラッカーファンとして、ドラッカーの著作の引用から「ドラッカーはこんな詩を飛ばす人間ではない」と言うことを広く伝えたいと思った。
これは、一度でもドラッカーの著作をちゃんと読んだことのある人なら分かると思う。ドラッカーは誰よりも真剣に社会の研究に取り組んでいたし、人間の幸せについても本気で考えていた。
生涯プロフェッショナルで、現役だった。そんな人が「生まれ直したらもっと不衛生に行きたい」だの「アイスクリームを食べたい」だの「世の中には真剣に悩むことなどない」だの言うわけがないではないか。
(あの詩が良い詩かどうかとは別問題。市井の人、84歳まで生きた老修道女の詩としてなら、可愛らしく味わい深いものだと思う。)
これは断言してもいいが、あの記事をブクマして「素晴らしい」「感動した」「95歳まで走りきった人だからこそ言える言葉」「ドラッカーならではの重み」だの賞賛している人は、ドラッカーの本を一冊も読んだことがない。一冊も、だ。「誰が書いたかは問題ではない。内容がいいのだ」という人もいる。
これらの人たちの間では、ドラッカーは「もっと裸足でいたかった人」「最後に人生を後悔した人」として記憶されることになる。ドラッカーが多分自国以外でもっとも注意と愛情を払ってくれていた、この日本で。
「誰が書いたかが問題ではない」はずがないではないか!
シャア・アズナブル「つまづいたっていいじゃないか にんげんだもの」
などと言われたら、内容が良くてもおかしい。
イエス・キリスト「加害行為は一気にやってしまえ」
とか、どうだろうか。
押尾学「くるしいことだってあるさ にんげんだもの」
とか、内容が良くてもおかしいではないか。
(※1と3は相田みつを、2はマキャベリです)
ブクマコメントなどを見ると、相変わらずあれを見て「これがドラッカーの詩である」と思う人は後を絶たないようだ。はてなSEOパワーによって「ドラッカー 詩」で検索するとあの記事が1位に来る。ネットで文章を読む人の中には、あの冒頭の注意文を読まない人も多いだろう。タイトルは「ドラッカー95歳の詩」で、記事にはそのまま
広告
以下原文
経営学の権威、マネジメントを作った男と称され、著書も多く世界中で長く読まれているピーター・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)が亡くなる95歳の時に書いた詩。
もう一度人生をやり直せるなら・・・・
と書かれている。そのまま信じる人がいても当然である。
Apelogさんに良心があるなら、どうしてあのタイトルと記事を改変しないのだろうか。
いや、僕はここに「ブログの記事は、一度アップしたら変えないのがマナー」という風潮があるのではないかと思う。確かに、参照やトラックバック、議論の流れなどで、途中で記事を変えられると困る場合もある。しかしそれはケース・バイ・ケースで、今回のように明らかに誤った情報や、個人の名誉を傷つけるような内容が広まる可能性がある場合にはその限りではないと思う。